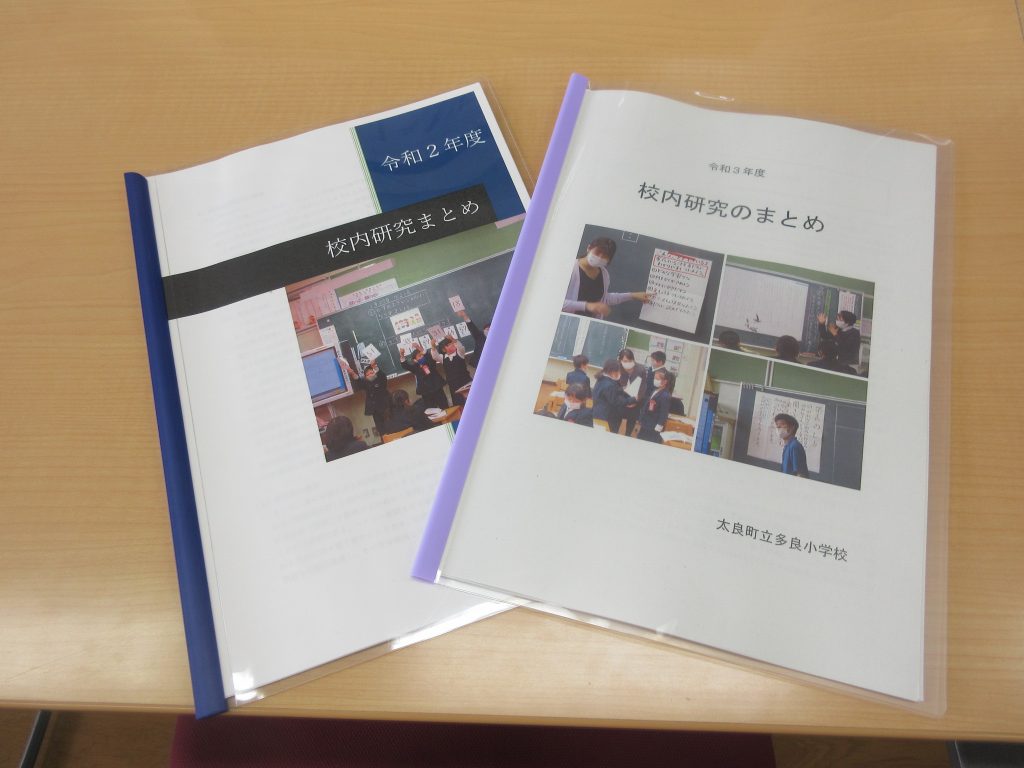今年度最後の研究推進委員会
入力日
2022年3月30日
閲覧数
1,194
3月30日(水)の午前中に、多良小学校では今年度最後の研究推進委員会を行いました。

取組1のペア研による各自、年間4回の授業研究会については、次年度も継続の方向で確認しました。
その中で、
1 特別支援学級の授業参観をもっとできるようにするアイディア
→特別支援教育は大切であり、(特に)若手教員は早い時期に見た方がよい。
→交流学級の担任は自分の学級に在籍する子どもがどのように学んでいるかを知った方がよい。
2 指導案の代わりとなる授業構想シート(A4)の様式
→負担軽減だけでなく、授業を行ったり参観したりするときに大切なことは?
→ねらい(どんな力を付けたいか?)、手立て(そのためにどのような工夫をするのか?)が確実に分かること。
3 「研究のまとめ」の個人の振り返りの様式
→授業構想シートとの連動
→ついつい反省めいたことを書きがちであるが、「成果と課題」という視点でうまくいったことや頑張ったことも書く方が元気につながる。
4 授業後のアンケートの項目
→アンケートをもっと活用できるようにする。
→「授業づくりのステップ123」との関連をもっと分かりやすくすることで、「学力向上対策評価シート」とも連携が深まるとよい。
→一人一台PCを活用したアンケート実施ができるように工夫し、集計等の負担を軽減する。
などについて、議論しました。
多良小学校の校内研究は、研究主任がぐいぐいリーダーシップを発揮して、「トップダウン型」で進めていくような研究ではなく、(少々時間はかかりますが)みんなが本音で建設的な意見を出し合い、いろいろなアイディアを積み上げていく「ビルドアップ型」の研究だなあとつくづく感じます。

今年度の研究主任の横山亜紀先生(教職4年目)は、先生方の意見をとりまとめつつ、その方向性をとりまとめていくコーディネーター役を務めてくれました。
取組2については、学校評価、人事評価の業績評価、各プロジェクトでの取組とを連動させて、一元的に進めることによって、教員の負担軽減を図りつつ、学校教育目標のよりよい実現につなげていくようにするための手立てであることを確認しました。
つまり、取組2については、「学校運営の中で、前述のことが学校の中でスタンダードになっていけば、将来的には『発展的解消』ということで、なくしてもよいのではないか」と考えています。
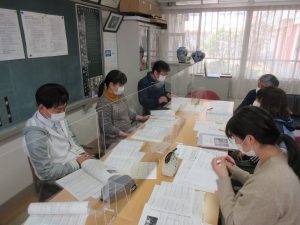
最後の研究推進委員会、お疲れ様でした。本日の話し合いが、令和4年度の研究によりよくつながっていくことを期待しています。
昨年度と今年度の「校内研究のまとめ」です。
(働き方改革の一つとして)比較的、お手軽に出来上がりますが、一人一人の先生方の顔が見えて、なかなか読み応えがある「校内研究のまとめ」となっています。