令和4年度 全国学力・学習状況調査の結果と対応について
入力日
2022年10月9日
内容
令和4年4月19日(火)に、小学校第6学年児童(と中学校第3学年生徒)を対象に実施されました全国学力・学習状況調査の結果について、本校児童の結果をお知らせいたします。
別添の報告では、調査結果を基に、本校児童の学力の傾向を分析し、学力向上についての対応策をまとめました。そ
の概要についてお知らせしています。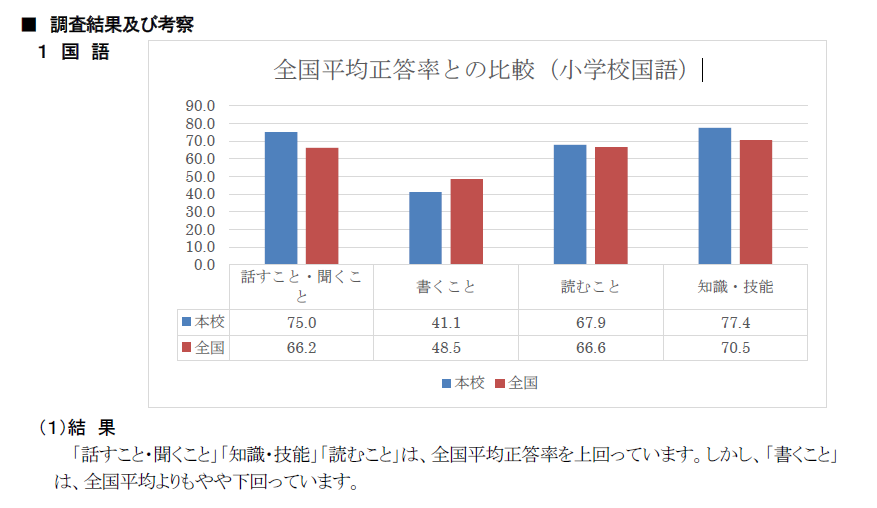
国語 学力向上のための取組
【学校では】
○子供が主体的に学べるように、授業の在り方を工夫すること(主体的・対話的で深い学び)で、子供同士が話し合いながら、深く学んでいけるようにします。
○目的や意図に応じて、自分の考えとその理由を明確にしながら書く機会を増やします。
○漢字の読み書き、ことわざ等の学習に一層力を入れるとともに、辞書を活用させ、語彙力を増やします。
○インタビュー、案内や紹介など、日常生活につながる言語活動を授業場面で設定します。【ご家庭では】
○音読を大切にしていきましょう。繰り返し音読することで、文の構成、言葉の意味を理解し、文節ごとにきちんと区切ってすらすら読めるようになります。文章を読み、要点や意図を捉えることは、国語科だけでなく全ての教科の学力向上に不可欠です。
○読書を大切にしていきましょう。文学・科学・歴史・地理・芸術…いろいろな本を読み、いろいろな表現や用語にふれることで、語彙力を高め、知識の幅を広げることができます。図書館や書店に定期的に行くことも、子供の読書習慣をつける上でおすすめです。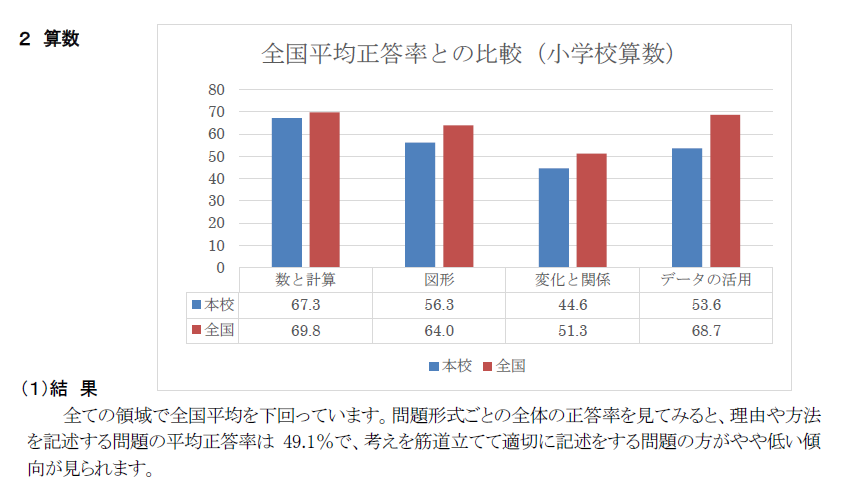
算数 学力向上のための取組
【学校では】
○式から答えを出すだけではなく、式の意味を考えたり、式に合う問題を作ったり、式から生活場面を想起できるような活動を進んで取り入れ、式、絵や図、具体的場面を行き来できるようにします。
○様々な見方や考え方ができるように、グループで話し合う活動を取り入れていきます。また、自分の考えを、式や言葉を使って、論理的に書く機会を増やし、記述力の向上に努めます。
○TT少人数指導、ノートチェック、プリント、ドリル、家庭への課題など、日々の指導の中で個々のつまずきを早期に発見し、補充指導に努めます。【ご家庭では】
〇お子さんが、宿題や自主学習(自学)をしているときに、今どのような学習をしているのか、理解できているのか、解くのにどのくらい時間がかかっているのか等、関心をもって見ていただきたいと思います。また、テストやドリル、プリント等にも目を通し、励ましや称賛の言葉をかけていきましょう。
〇生活場面で算数を使ってみてください。料理の時に食材の重さを量ると、量感が身に付きます。車で出かけるときに、「時速〇㎞で△分かかったから、距離は約□㎞」と計算してみましょう。「習った 事が生活で使えておもしろいな」という経験を重ねることが、算数好きになる第一歩です。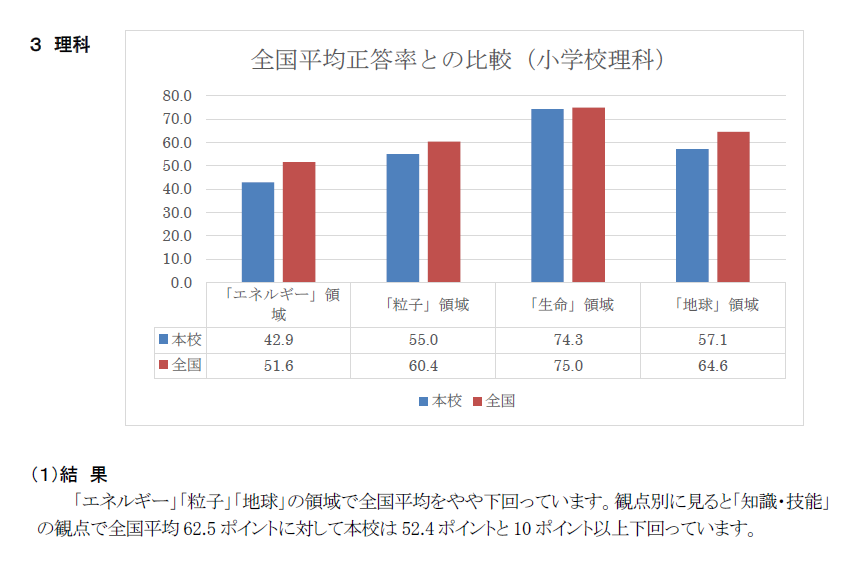
理科 学力向上のための取組
【学校では】
○目的意識をもった実験・観察を行うための基礎的・基本的な知識・技能の定着を図ります。
○理科の学習過程を「事象提示→課題→予想→実験・観察→結果→考察→課題・・・」とし、一貫した学習指導を行うことにより、児童の思考力、判断力、表現力の向上を図ります。
○様々な見方や考え方ができるように、グループで話し合う活動を取り入れていきます。また、結果に対する考察を論理的に書く機会を増やし、記述力の向上に努めます。【ご家庭では】
○お子さんの宿題プリントやテストをご覧になって、励ましや称賛の言葉をかけてください。
○理科に興味・関心をもたせるための手立てとして、「習ったことが生活の中で使えて、便利だな。おもしろいな。」と思う経験をさせることが有効です。星空を見上げて星座の話をしたり、コップの結露の理由を考えたりすることで、習ったことと日常生活での現象を結びつけると理解が深まることもあります。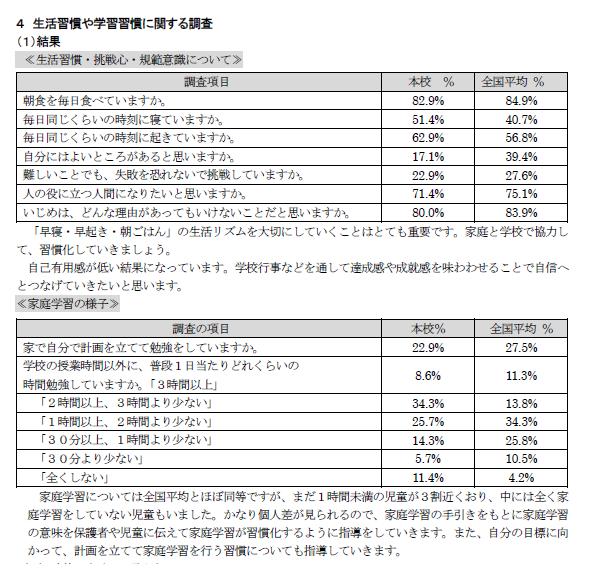
改善に向けての取組
【学校では】
○子どもたちが「深い学び」に向かうよう、職員が共通理解をもって授業改善に取り組んでいます。授業展開は良かったか、教師の問いかけにより子どもたちが深く考えるきっかけになったか等を振り返り、次の授業へ生かすようにしています。今後も全職員が熱意をもって取り組んでいきます。
○読書の機会を増やすための工夫をしていきます。始業前(8:05~8:15)に朝の読書タイムを設けたり、ボランティアによる読み聞かせをしたりするなど、これまでにも取り組んできたことを、これからも継続していきます。
○これまでに学習してきた内容、特に前学年に学習してきた内容が定着するよう、朝のスキルタイム等
を活用し、定期的に復習していきます。【ご家庭では】
○上記の項目は、改善を図ろうと「まなざしカード」でも取り上げている項目です。「まなざし週間」だけでなく、規則正しい生活と家庭学習の定着することは、極めて大切なことです。お子さんが自分からできたとき、少しでも向上したときを逃さず、褒めることで意識が更に高まります。
○「家庭学習の手引き」をご覧になり、学習時間のめやすや、自主学習の説明を参考に、自分で決めて学習できるように励ましてください。詳細は、別添のファイルをご覧ください。
閲覧数
558
ファイル
