雅楽の学習(6年)
入力日
2025年2月21日
閲覧数
377
金立小学校では毎年、音楽の学習で「越天楽今様」という曲を学習する時期に、「越天楽」という曲を含む「雅楽」という音楽について、雅楽の演奏をされる方に来ていただいてレクチャーとワークショップを開いてもらっています。


今年度は、2月17日(月)の5、6時間目に金立小学校に来ていただきました。
最初に「雅楽」という音楽がどのような音楽なのかということを教えていただきました。


一言に「雅楽」といっても、楽器のみで演奏する「管絃」、舞(踊り)を伴う「舞楽」、歌を伴う「歌謡」などがあるとのことでした。「雅楽」の演奏では、この日に紹介してもらう「篳篥」(ひちりき)「龍笛」(りゅうてき)、「笙」(しょう)が中心であるということで「三管」と呼ばれるそうです。
それぞれの楽器についても、その構造などを教えていただき、どんな音がするかも聴かせていただきました。
【笙】
細長い竹の管を17本集めた楽器で、実際はその中の15本で演奏をするそうです。この楽器は息を吸っても吐いても音が出る楽器で切れ間なく音を出し続けることができるそうです。伝説の鳥「鳳凰」が羽を休めている姿に似ていることから、「鳳笙」と呼ばれることもあるそうです。笙は和音を出すことができる楽器であり、その音は「天から差し込む光」を表しているといわれるそうです。



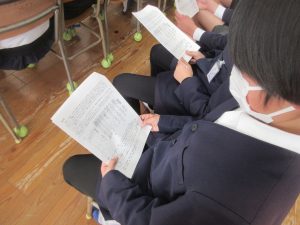
【篳篥】
「舌」と呼ばれるダブルリードで音を出すそうです。楽器の大きさに比べるととても大きな音が出る楽器で演奏では主な旋律を演奏する楽器だそうです。篳篥の音は地上で生活する人間の声を表しているといわれるそうです。


【龍笛】
雅楽で使われる横笛にはほかにも種類があるそうです。篳篥に比べると音域(音が出せる範囲)も広く、篳篥の主な旋律を飾るように演奏される楽器だそうです。名前にもあるように、龍笛の音は空を舞う龍の鳴き声を表すといわれているそうです。


最初に全体の調子を合わせる「音取り」(ねとり)という演奏があることや、雅楽の楽譜は元々はなかったことなども教わりました。楽士(演奏する人)がメモのように残したものが現在の楽譜になっているとのことでした。


いよいよ、雅楽「越天楽」を演奏してもらいました。




後半はワークショップです。実際にいろいろな楽器の演奏を体験しました。上手に音を出している子どもたちもたくさんいました。なかなか難しいのにすばらしいですね。




今年の6年生はなかなか筋がいいそうです。




普段は手にすることもできないような雅楽の楽器を実際に演奏できる子どもたちは幸せですね。






今年度もありがとうございました。6年生はこの学びをしっかりと記憶に留めておいてくださいね。中学校の音楽の授業では、雅楽「越天楽」という音楽を鑑賞することと思います。そのときに、この演奏体験などが生きるとよいですね。

